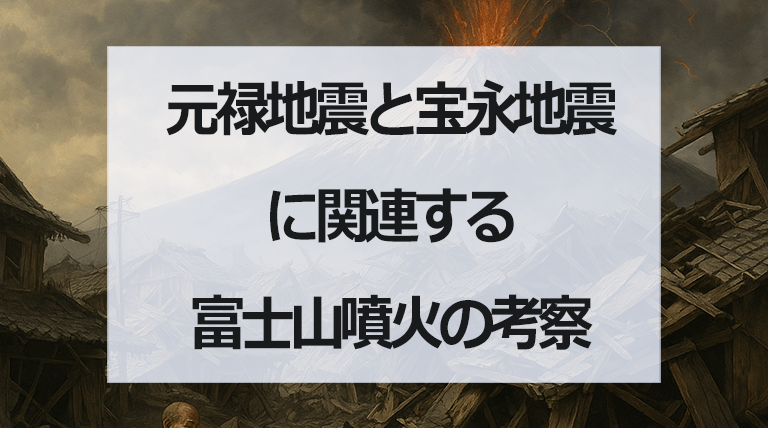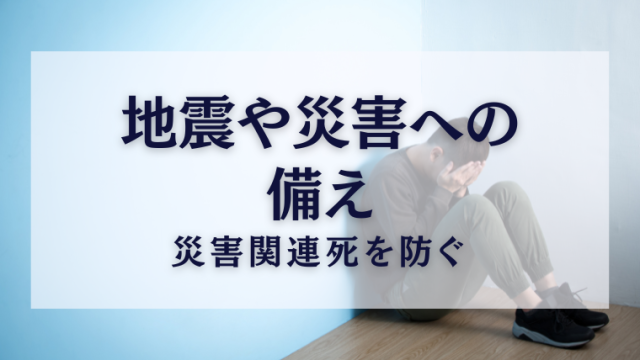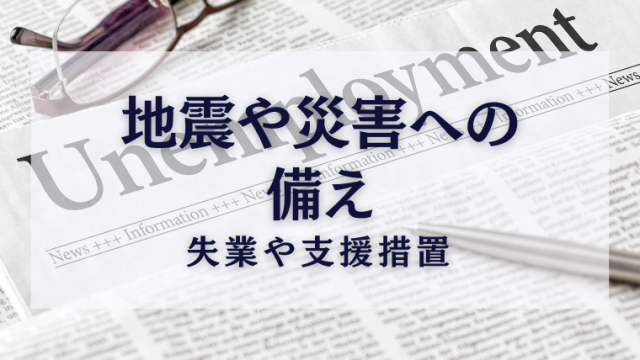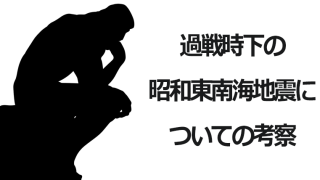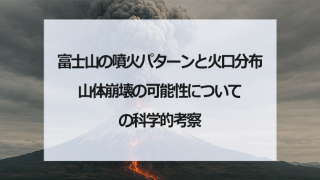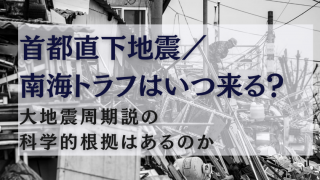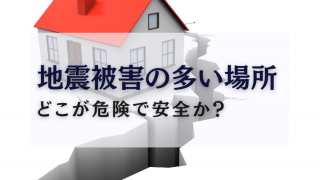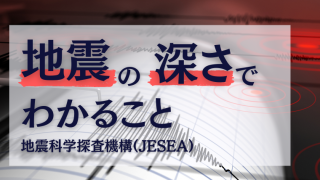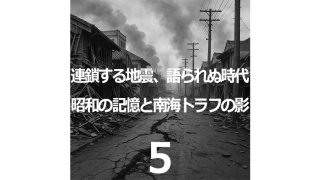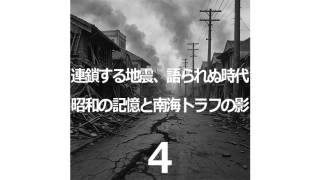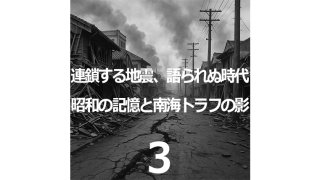日本は世界有数の地震多発地帯であり、歴史的にも多くの大地震と火山噴火が記録されている。その中でも、元禄地震(1703年)と宝永地震(1707年)は特に重要な地震であり、宝永地震の直後には富士山が大噴火を起こした(宝永噴火)。これらの地震と富士山噴火の関係について考察する。
1. 元禄地震とその影響
元禄地震は1703年12月31日に発生したマグニチュード8.1前後の巨大地震で、震源は房総半島南部の海域とされている。この地震により、関東地方を中心に甚大な被害が生じ、江戸(現在の東京都)でも強い揺れが観測された。
この地震の影響として、注目すべきは富士山の鳴動である。元禄地震の後、富士山では噴火には至らなかったものの、山体の異常な活動が記録されている。具体的には、地震後に火口周辺での地鳴りや軽微な噴気活動が報告されており、地下のマグマ活動に何らかの影響を与えていた可能性がある。
2. 宝永地震と富士山噴火
元禄地震の約4年後、1707年10月28日に宝永地震が発生した。この地震は南海トラフ沿いで発生したマグニチュード8.6前後の巨大地震で、東海・東南海・南海の三連動型地震だったと考えられている。この地震による津波は広範囲に及び、高知県や和歌山県の沿岸部では最大10mを超える波が押し寄せた。加えて、建物の倒壊や地盤の隆起・沈降などの被害も甚大であった。
この宝永地震の約49日後、1707年12月16日に富士山が大噴火を起こした。これは「宝永噴火」として知られ、富士山史上最大級の噴火の一つである。この噴火では、大量の火山灰が関東地方まで降り積もり、特に江戸では昼間でも暗くなるほどだった。この噴火の特徴として、溶岩流を伴わず、主に火山灰や軽石が大量に放出されたことが挙げられる。
3. 地震と富士山噴火の関係
地震が火山噴火を誘発するメカニズムについては、現在も研究が進められているが、一般的には以下のような影響が考えられる。
1.地震によるマグマの上昇促進
大地震による地殻の歪みが、地下のマグマ溜まりに影響を与え、圧力の変化によってマグマが上昇しやすくなる。
2.火道の形成
地震による断層運動や割れ目の形成が、火山内部のガスやマグマの通り道を作り、噴火を誘発する可能性がある。
3.地下水の影響
地震によって地下水の流動が変化し、それがマグマの噴出を助長することがある。
元禄地震の際には噴火には至らなかったものの、鳴動が記録されていることから、地震によって富士山の地下のマグマに影響が及んでいたと考えられる。一方、宝永地震の際には、約49日後に実際の噴火が発生しており、地震と噴火の間に強い関連があった可能性が高い。
4. まとめと現代への示唆
元禄地震と宝永地震は、いずれも日本列島に大きな影響を与えた歴史的な巨大地震である。元禄地震後の富士山の鳴動は、地震が火山活動に影響を与える可能性を示唆しており、宝永地震後の噴火はその具体例と言える。
近年、日本列島では南海トラフ地震や首都直下地震の発生が懸念されている。これらの地震が発生した場合、富士山を含む火山活動にも影響を及ぼす可能性があるため、地震と火山の相互作用についての研究を進めることが重要である。過去の事例を参考にしつつ、現代の観測技術を活用して火山活動の監視を強化し、適切な防災対策を講じることが求められる。
元禄地震と宝永地震の事例は、巨大地震と火山噴火の関係を考察する上で貴重な歴史的資料であり、今後の防災計画にも重要な示唆を与えるものである。