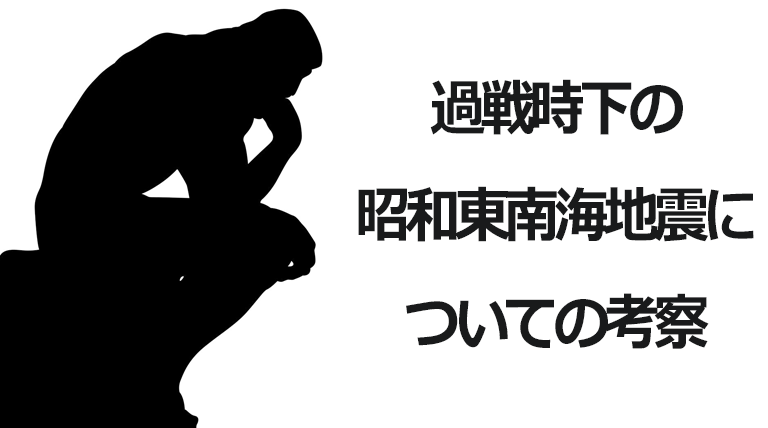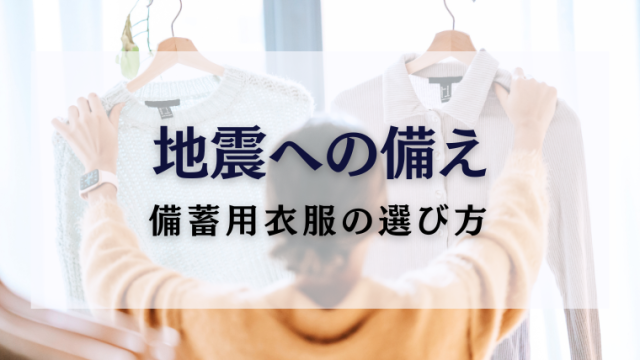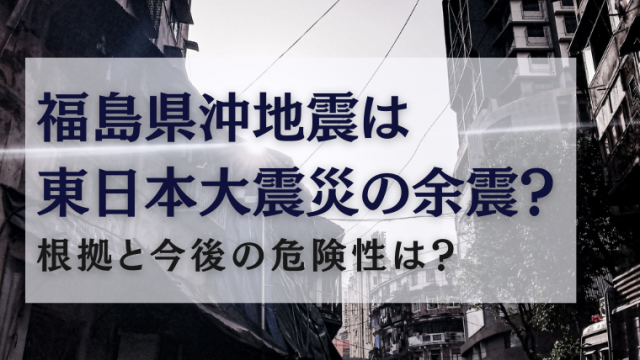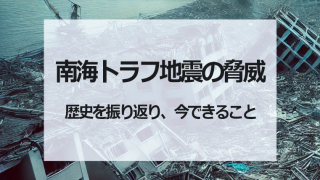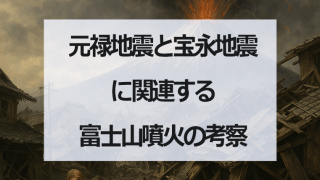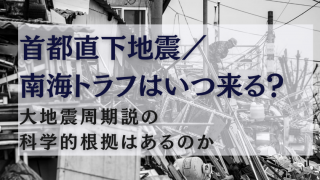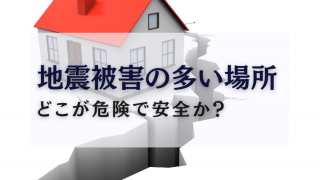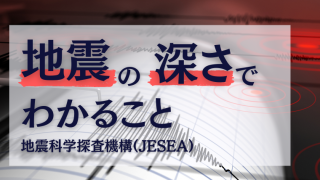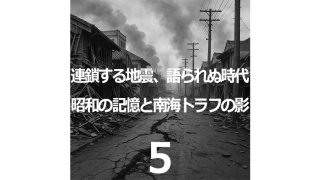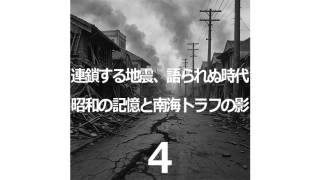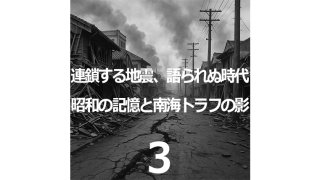1. 昭和東南海地震の概要
昭和東南海地震は、1944年(昭和19年)12月7日に発生した大地震であり、東海・近畿地方を中心に甚大な被害をもたらした。マグニチュード7.9と推定されるこの地震は、東南海トラフ沿いで発生したプレート境界型地震であり、津波や液状化現象、建物の倒壊などによる多数の犠牲者を出した。しかし、この地震の被害状況は、当時の戦時体制下における厳しい報道管制によって詳細に報じられることはなかった。
2. 報道管制と政府の対応
当時の日本は太平洋戦争の最中であり、戦局は次第に悪化していた。政府および軍部は国民の動揺を防ぎ、戦意を維持するために、自然災害に関する情報を厳しく統制していた。昭和東南海地震の発生直後、政府は報道機関に対し、地震の被害を最小限に伝えるよう指示し、大規模な被害の発生についての公表を制限した。このため、多くの国民は実際の被害の深刻さを知らされず、救援活動も十分に行われなかった。
この報道管制の影響は大きく、特に軍需工場や交通インフラへの被害はほとんど報じられなかった。地震による被害が明らかになることで、戦争遂行に支障が出ることを恐れた軍部が情報統制を強化した結果、被災者の救援や復興が遅れる要因となった。
3. 中島飛行機半田工場の被害と影響
昭和東南海地震によって壊滅的な被害を受けた施設の一つが、中島飛行機の半田工場である。中島飛行機は当時、日本最大の航空機メーカーの一つであり、戦争遂行のために重要な軍用機の生産を担っていた。半田工場では主に陸軍の主力戦闘機「疾風」などが製造されていたが、地震による工場の倒壊と火災により、生産ラインが壊滅的な打撃を受けた。
この被害は日本の航空戦力に大きな影響を与えた。すでに戦況が悪化し、航空機の損耗が激しくなっていた中での工場壊滅は、戦力の回復を困難にした。軍部は復旧を急いだものの、資材や労働力の不足により、十分な再建ができないまま戦争終結を迎えた。
4. 工場で働いていた中学生や女学生の犠牲
中島飛行機半田工場には、多くの若年労働者が動員されていた。戦時下では、労働力不足を補うために学徒動員が進められ、中学生や女子学生が軍需工場で働いていた。彼らは過酷な労働環境のもとで航空機の製造に従事していたが、昭和東南海地震の発生により、多くの生徒が工場の倒壊や火災によって命を落とした。
特に、彼らは十分な避難訓練を受ける機会もなく、工場の建築構造も耐震性に乏しかったため、建物の下敷きになって圧死するケースが多発した。また、当時の日本はすでに物資不足が深刻化しており、救援や医療体制も不十分であった。そのため、助かる可能性があった負傷者も適切な治療を受けられず、多くが死亡した。
5. 地震被害の隠蔽がもたらした影響
昭和東南海地震の被害が適切に公表されず、十分な対策が取られなかったことは、戦後の防災政策にも大きな教訓を残した。戦時体制下においては、国民の安全よりも戦争遂行が優先された結果、被災者への救援が遅れ、被害が拡大した。このような情報隠蔽の弊害は、戦後の防災政策において透明性の重要性を認識させる契機となった。
戦後、日本は高度経済成長を遂げる中で、防災意識の向上に努め、建築基準の強化や地震対策の充実を図った。
6. 結論
昭和東南海地震は、戦時中の情報統制の下で、その被害の実態が十分に伝えられなかった悲劇的な災害であった。特に、中島飛行機半田工場の被害は、日本の航空戦力に致命的な打撃を与えただけでなく、多くの若年労働者の尊い命を奪った。
この地震の教訓は、単に防災対策の必要性を示すだけでなく、情報公開の重要性をも浮き彫りにしている。自然災害に対する正確な情報の提供と迅速な救援活動が、いかに多くの命を救うかを考えさせられる事例であり、今後の防災政策においても決して忘れてはならない歴史の一幕である。