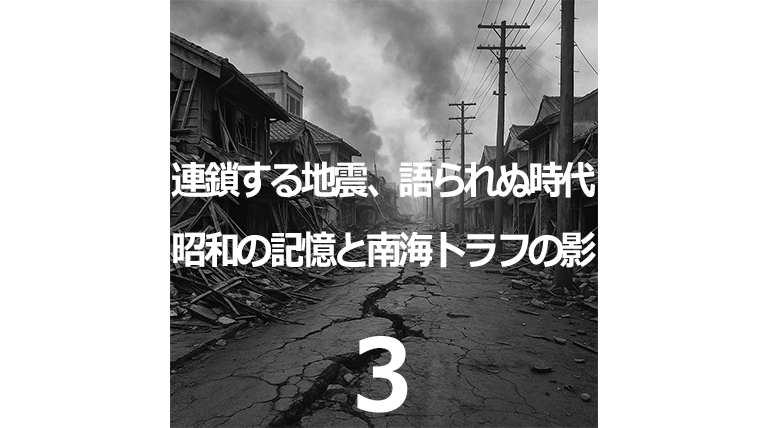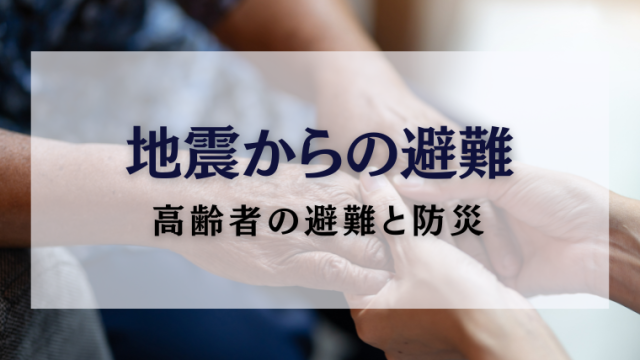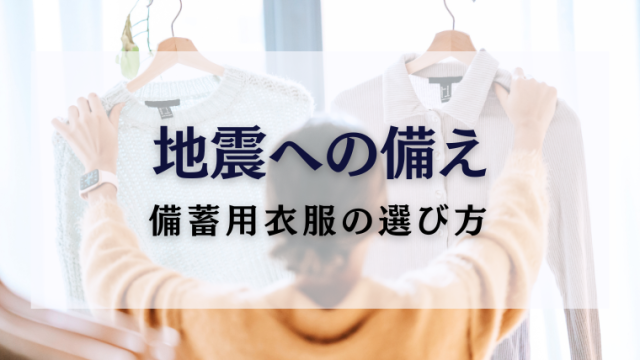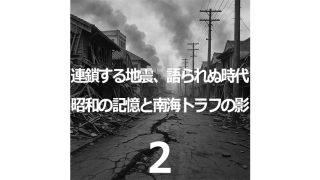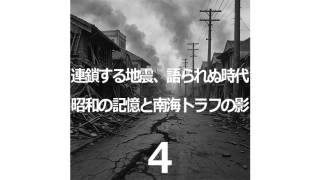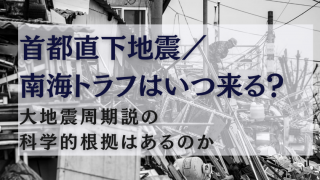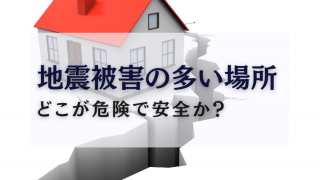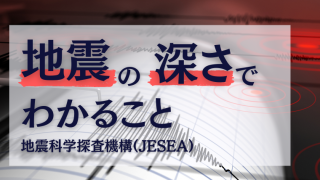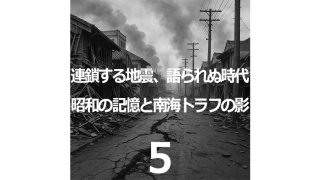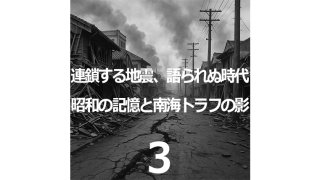【第3部】南海地震──占領下で発生した“忘れられた巨大地震”
1946年12月21日、午前4時19分。まだ夜が明けきらない早朝、西日本の太平洋側を激しい揺れが襲った。昭和南海地震。地震の規模はマグニチュード8.0。和歌山、高知、徳島、愛媛といった地域を中心に甚大な被害をもたらしたこの地震は、東南海地震、三河地震に続く“第三の連鎖”として語られるべき出来事である。
しかし、終戦からわずか1年4ヶ月という時期だったこともあり、人々の生活はまだ混乱の渦中にあった。瓦礫の町にバラックが立ち並び、闇市が日常の一部だった。敗戦国となった日本は、焦土からの再出発に追われ、地震への備えや記録は後回しにされがちだった。
最も深刻な被害が出たのは高知県だった。特に室戸市や高知市の沿岸部では津波が押し寄せ、家屋が根こそぎ流された。犠牲者の多くは逃げ遅れた高齢者や子どもであり、避難の指示も届かぬまま、夜明け前の暗闇の中で命を落とした。
徳島県南部では、地盤の液状化や河川の氾濫が追い打ちをかけた。橋が落ち、鉄道が寸断され、復旧には数ヶ月を要した。電気・ガス・水道といったインフラの停止は、人々の生活を直撃した。避難所では食料と毛布が不足し、配給も間に合わなかった。
当時の高知新聞には、「海鳴りとともに黒い壁のような波が押し寄せた」との証言が掲載されている。だが、紙面の多くは占領政策に関する記事に割かれ、地震の被害詳細には大きな枠は与えられなかった。情報の流通手段が限られていた時代、地方の惨状は都市部に届きづらかった。
地震と津波による犠牲者は、公式には1000人余りとされているが、実際の数はそれ以上だったともいわれる。農村部では戸籍が失われ、正確な人数を記録できなかったケースも多かった。漁村では、港が壊滅し、生業を奪われた人々が都市部への流出を余儀なくされた。
当時の日本は、ようやく占領軍による統治が始まり、憲法草案が議論される時期でもあった。そのような国家的な大転換期にあって、地方で起きた自然災害は、国全体の記憶としては埋もれていった。
しかし、この南海地震こそ、昭和東南海・三河地震に続く一連の“連動地震”の締めくくりであった。三つの巨大地震が、わずか2年の間に次々と発生した事実は、日本の地震史上でも極めて特異である。
高知県のある中学校には、当時の教師が書き残した記録が保管されている。「津波が来るぞ、と叫んだが、子どもたちは何が起きているのか分からなかった。泣きながら山へ逃げたその姿が忘れられない」。その記録は、今も小さな郷土資料館の片隅にひっそりと展示されている。
南海地震によって再び家を失った人々は、「もう二度と家を建てない」と言い残して海辺を離れていった。彼らの中には、東南海や三河でも被災経験を持つ者もいた。繰り返される地震と津波。それは「想定外」という言葉では片づけられない、現実としてそこにあった。
復興の中で、都市のインフラは少しずつ整えられ、住宅も再建されていったが、心の傷はそう簡単には癒えなかった。被災者たちは、語られないまま新しい生活に埋もれていった。
やがて時代が進み、経済成長の波が日本を包み込むと、こうした“戦後災害”の記憶はより一層忘れ去られていく。だが、昭和南海地震は単なる過去の災害ではなく、繰り返される「連鎖」の一部であったという事実を、私たちは軽んじてはならない。
私たちは、この“第三の地震”が語られることの少なさに、改めて目を向ける必要がある。過去の災害は、ただの歴史ではない。次の災害への道しるべである。
そして今、南海トラフ巨大地震が懸念される時代に私たちは生きている。あの昭和の3連動地震の記憶をどう継承し、どう備えるか。それが、次の世代に対する私たちの責任である。
(第3部・了)