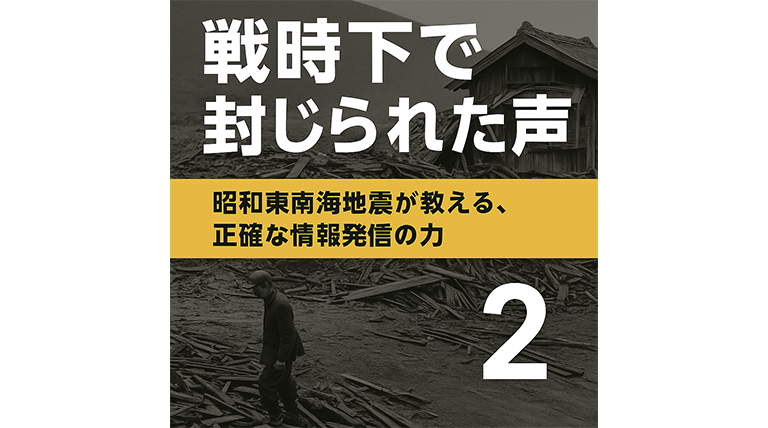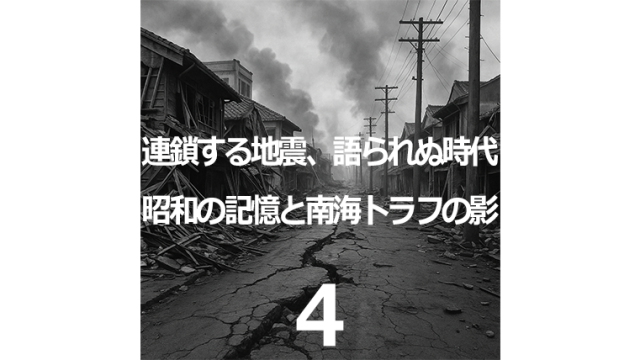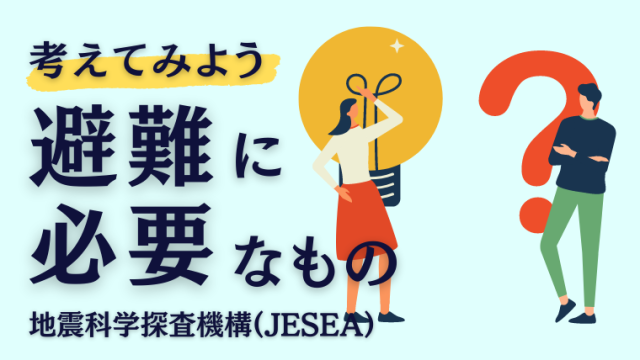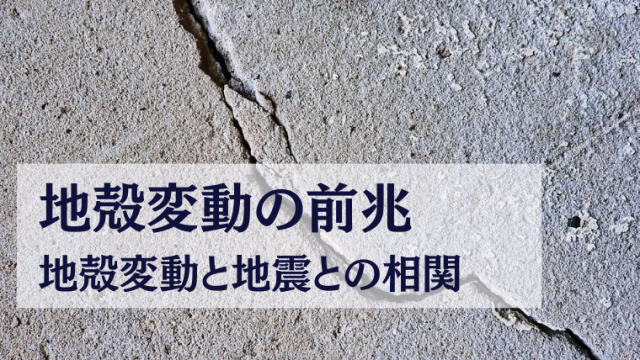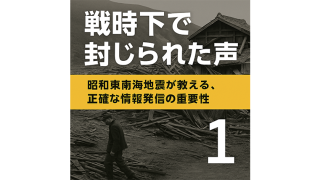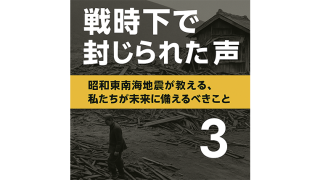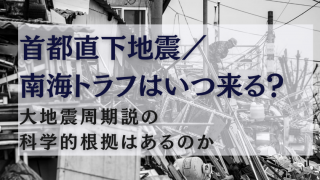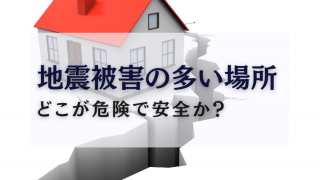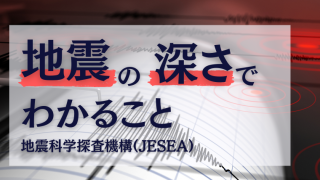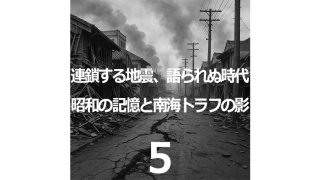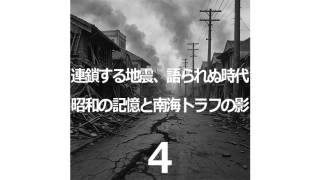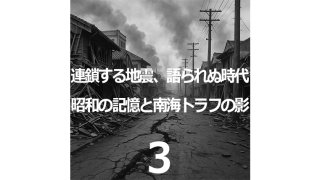1944年12月7日、太平洋戦争末期の日本を襲った昭和東南海地震。
紀伊半島沖を震源とするこの巨大地震は、マグニチュード7.9を記録し、東海・近畿地方を中心に壊滅的な被害をもたらしました。
しかしその実態は、当時の報道管制によって国民にほとんど知らされることなく、被災地は孤立し、多くの命が救われることなく失われました。
本記事では、前回に続き、正確な情報が人々を動かし、社会全体の命を守る力になるという視点から、災害時の情報発信の意義について掘り下げます。
報道されなかった「現場の声」
地震が発生した当時、政府は「戦意を喪失させてはならない」として、新聞社に対し被害の報道を極めて抑えるよう指示しました。
当日の夕刊では、「関西地方に小規模の地震」というような扱いにとどまりました。
そのため、東海地方の外に住む人々は、事態の深刻さに気づくことができず、救援の動きも鈍化しました。
現地では、家屋が倒壊し、多くの人が下敷きになっていましたが、支援の到着が遅れたことにより、助かるはずだった命が数多く失われました。
また、津波や火災の被害も相次ぎましたが、そうした情報すら、十分に届くことはありませんでした。
情報が届かないことで生じる「二次災害」
災害において、一次的な被害より深刻になりうるのが「情報の欠如」による二次災害です。
昭和東南海地震では、避難の遅れ、物資の不足、医療支援の停滞が深刻な被害を拡大させました。
特に、医療機関の混乱や、被災地の孤立は甚大でした。
「支援が来る」と信じて待ち続けた人々が、誰にも発見されることなく命を落としたケースも記録されています。
また、一部地域では「敵の破壊工作ではないか」というデマが広がり、不安と混乱を助長したことも報告されています。
このように、情報が届かない・誤った情報が広がるという状況は、災害におけるリスクをさらに増幅させるのです。
正しい情報が「人を動かす力」になる
では、もし当時、正しい情報が全国に共有されていたらどうなっていたでしょうか。
他県からの医療支援、避難誘導、食料の供給、炊き出しの実施など、より早く、的確な支援体制が築かれていた可能性があります。
**情報は「人を動かす力」であり、「命をつなぐ手段」**です。
どこで何が起きているかを正確に知ることができれば、行動の判断が生まれます。
しかし、情報が届かなければ、判断も行動も生まれず、人は孤立し、命を落とす危険性が高まります。
このような災害時の「情報の価値」は、現代の私たちにも強く問いかけてきます。
次回の記事では、現代の情報社会において、私たち一人ひとりが情報とどう向き合うべきか、そして災害時の情報発信と受け手の責任について掘り下げます。(次号第3弾にて詳細記載)
まとめ:過去の声が今を照らす
昭和東南海地震で失われた命の多くは、「地震そのもの」ではなく、「情報が封じられたこと」によって失われたとも言えます。
それは決して、過去の出来事として片付けてよい話ではありません。
情報が生命線となる現代においても、同じ過ちを繰り返さないために、私たちはこの歴史を学び、活かさねばなりません。
情報は、発信されるべき声であり、命を守る手段です。
そしてそれを正しく使えるかどうかは、私たち一人ひとりの意識にかかっているのです。
次回は、現代の災害対応における情報リテラシーと発信者責任について、より深く考えていきます。
どうぞ引き続きお読みください。