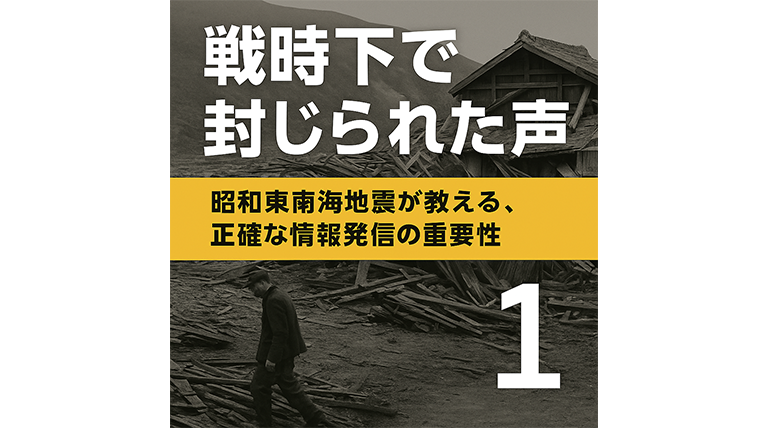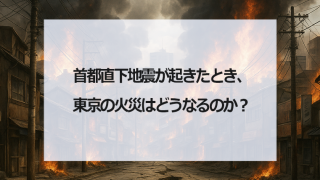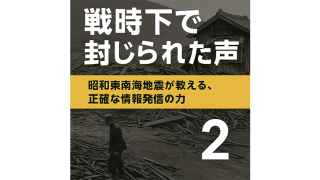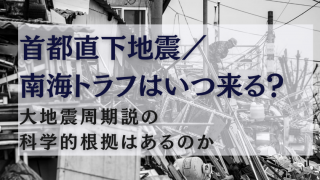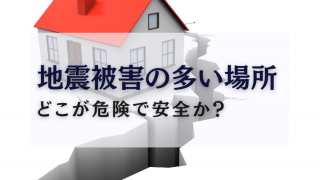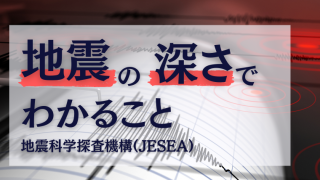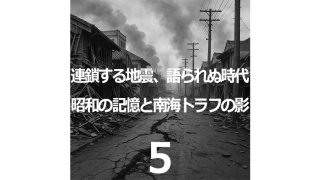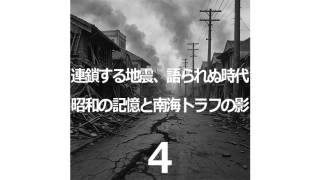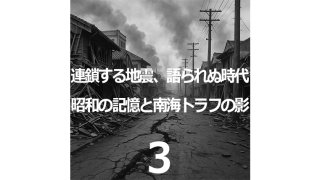1944年12月7日、太平洋戦争のさなか、日本列島を襲った巨大地震がありました。昭和東南海地震です。
この地震は、紀伊半島から東海地方一帯にかけて甚大な被害をもたらしましたが、当時は戦時体制下。厳しい報道管制が敷かれ、被害の実態は国民にも、地方にも、十分に知らされませんでした。
その結果、救援の遅れや二次災害が相次ぎ、多くの命が失われたのです。
この歴史は、現代に生きる私たちに、災害時における「正確で迅速な情報発信」の大切さを強く教えてくれます。
この記事では、昭和東南海地震を振り返りながら、災害と情報の関係について考えます。
報道管制下で起きた大災害
昭和東南海地震は、マグニチュード7.9。
死者・行方不明者は合わせて1223人にのぼり、住家全壊は約7万5千棟、半壊も含めると13万棟を超えました。
特に三重県や愛知県、和歌山県では、津波による壊滅的被害も重なりました。
しかし、当時の日本政府はこの惨状を「国民の戦意喪失を防ぐため」という理由で隠しました。
新聞やラジオでは、被害を過小に報じ、正確な状況は国民に伝えられませんでした。
これにより、近隣県や全国各地からの救援活動は大幅に遅れ、孤立した被災地では、負傷者が治療を受けられずに亡くなるケースが相次いだと記録されています。
本来であれば、全国から迅速な支援が届いていたはずでした。
しかし情報が隠されたことで、誰も助けに来られず、多くの命が失われてしまったのです。
情報が届かないことの「二次災害」
災害において、正確な情報が伝わらないと、直接の被害に加え、二次災害が発生します。
たとえば、火災、感染症、孤立による餓死や衰弱死などです。
昭和東南海地震では、こうした二次災害の被害拡大も大きな問題となりました。
また、間違った情報が広がることで、無用な混乱やパニックを招く恐れもあります。
このとき、国民の間では「敵国のスパイによる破壊工作」というデマまで広がり、不安がさらに高まったとも伝えられています。
災害の被害そのもの以上に、「情報の欠如」が命を奪う。
これが昭和東南海地震から得られる、大きな教訓の一つです。
正確な情報がもたらす「命綱」
では、もしこのとき正確な情報が発信されていたら、どれほどの命が救われたでしょうか。
地震直後に被害状況が正確に共有されていれば、隣県や中央から迅速に救援隊が派遣され、食糧や医療支援が届き、避難所の設営も早まったはずです。
孤立した村々にも、救いの手が早く差し伸べられたかもしれません。
現代では、SNSやスマートフォンの普及によって、個人でもリアルタイムに情報を発信できる時代となりました。
しかし一方で、誤った情報やフェイクニュースが広がるリスクも抱えています。
だからこそ、災害時には、
• 公式発表や専門機関の情報を確認すること
• 確認が取れない情報を拡散しないこと
• 必要な情報を正確に、簡潔に伝えること
が求められます。
情報は、混乱を防ぎ、人々を守り、命を救う「命綱」なのです。
最後に
昭和東南海地震から80年が過ぎようとしています。
あの時失われた多くの命は、「地震そのもの」ではなく、「情報が届かなかったこと」によって失われたとも言えるでしょう。
私たちはこの教訓を決して忘れてはなりません。
災害時には、まず落ち着き、正しい情報を迅速に届けること。
そして、受け取った情報を冷静に見極め、行動に移すこと。
これらの積み重ねが、多くの命を守り、未来の悲劇を防ぐことにつながるのです。