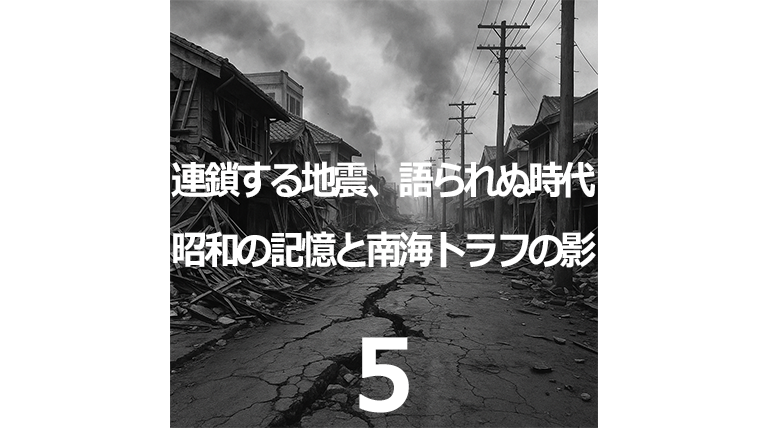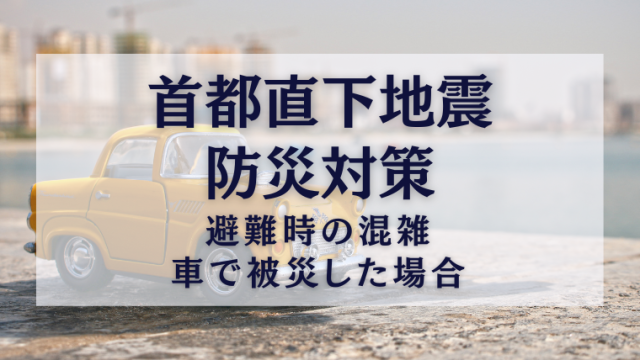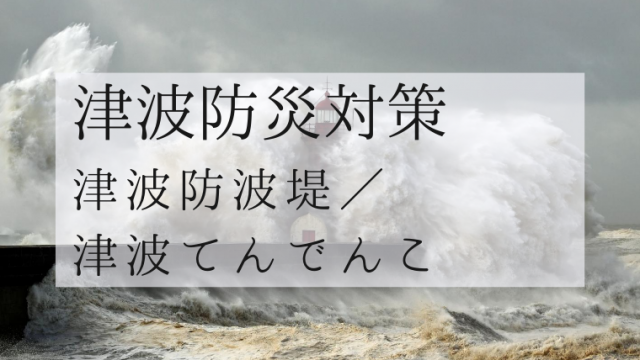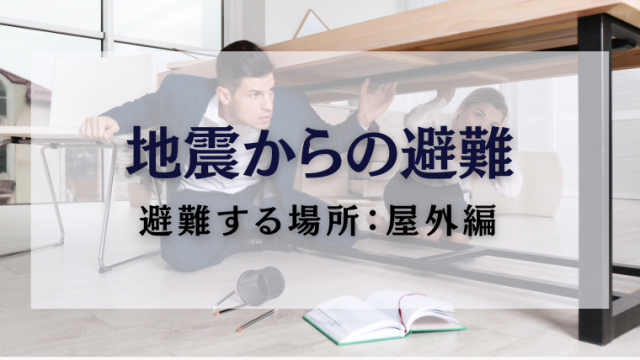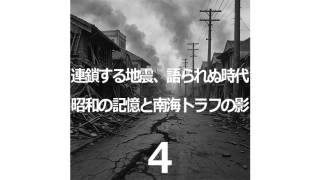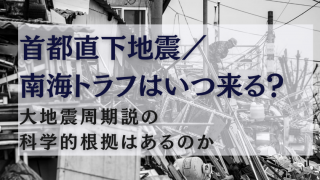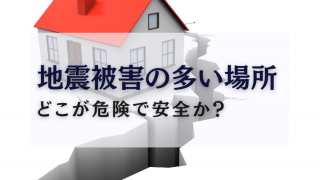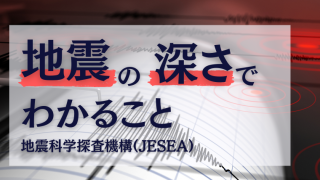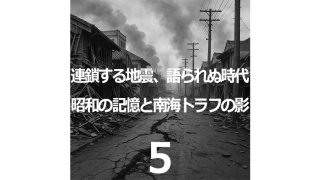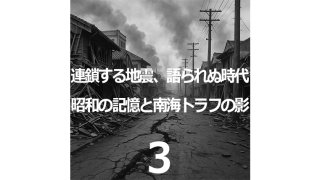【第5部】次の南海トラフ──歴史が教える備えなき連鎖
昭和の時代、日本列島は短期間に三度、巨大地震に見舞われた。東南海地震、三河地震、そして南海地震。1944年から46年にかけてのこの“地震の連鎖”は、過去の出来事として歴史の片隅に追いやられているが、その教訓はいまだに十分に活かされているとは言いがたい。
とりわけ、昭和南海地震を最後に70年以上が経過し、いま再び「次の南海トラフ巨大地震」が現実味を帯びてきている。政府の地震調査委員会によれば、今後30年以内にマグニチュード8〜9級の巨大地震が南海トラフ沿いで発生する確率は70%以上とされる。
もし昭和期と同じような連鎖が再び起これば、日本の社会や経済はどのような影響を受けるのか──。
昭和の時代と現代では、当然ながらインフラや情報網は格段に進化している。防災計画も、ハザードマップも、津波警報システムも整備されている。だが、根本的に変わっていないものもある。それは「人の弱さ」と「忘却の早さ」だ。
当時と比べ、都市部の人口密度ははるかに高くなり、高層ビルや交通インフラは複雑化している。巨大地震が都市圏を直撃すれば、交通の混乱、ライフラインの断絶、情報の錯綜といった事態が同時多発的に起こる可能性がある。昭和の時代以上に、被害の規模と影響は甚大になることが予想される。
そして、もうひとつの問題は「備えの格差」だ。自治体によって備蓄の状況や避難計画の精度に差があり、情報弱者や高齢者、障がい者が置き去りにされる恐れがある。地域コミュニティの希薄化も、避難や救援活動に影を落とす。
昭和の連鎖地震では、軍事・戦時体制という特殊な環境の中で被災者が声をあげられず、記録も記憶も埋もれていった。だが、今私たちは自由な社会に生きている。語り、記録し、伝える責任を果たすことができる──いや、果たさねばならない。
未来の災害に備えるということは、単に非常食を買い揃えることでも、耐震工事を施すことだけでもない。「過去を知ること」そのものが、最大の備えとなる。過去に何が起きたのか、なぜ備えが間に合わなかったのか、そしてどんな悲劇が繰り返されたのか。
ある遺族はこう語った。「津波で家族を亡くした祖父は、海の音を聞くとしばらく動けなくなった。それでも祖父は、毎年あの地震の話をしてくれた。怖かったこと、悔しかったこと、助けられなかったこと──それが私にとっての防災教育だった」。
今を生きる私たちは、こうした“記憶の継承”にもっと真剣に向き合うべきだ。マニュアルではなく、人から人へ伝える言葉こそが、命を守る力になる。
そして、次に来る南海トラフ地震が、単なる自然災害として終わらぬようにするためにも、私たちは「歴史に学び、いま備える」ことが求められている。
昭和の記憶とともに歩むこの5部作の最後に、ひとつの問いを残したい。
──次に起こる災害で、私たちは誰かを“語られぬ存在”にしてしまわないだろうか?
それを避けるために、できることはまだあるはずだ。
今こそ、あの3連動の歴史から、何を学び、何を伝えるべきか。その問いが、私たち一人ひとりに突きつけられている。
かつての被災者の言葉に、「あの日、誰も本当のことを教えてくれなかった。だから、自分の子どもには必ず話す」とあった。その言葉は、ただの親子の会話ではない。ひとつの地域の記憶であり、社会が次に備えるための“礎”である。
災害を経験しなかった世代が、どうそれを引き継ぐか──その橋渡しが今、私たちの手に委ねられている。
(第5部・了)