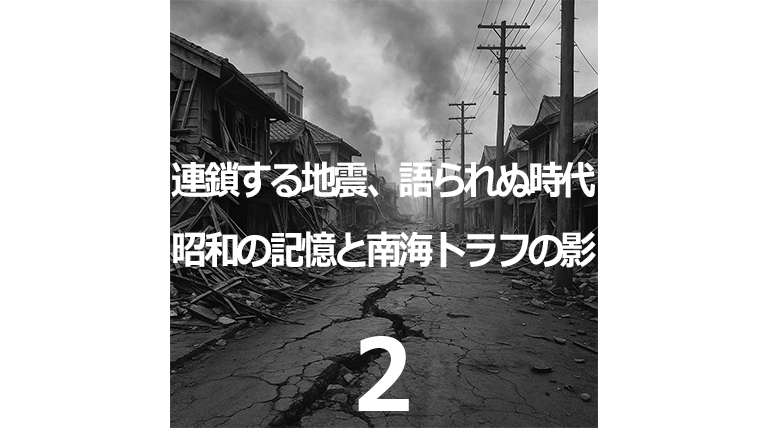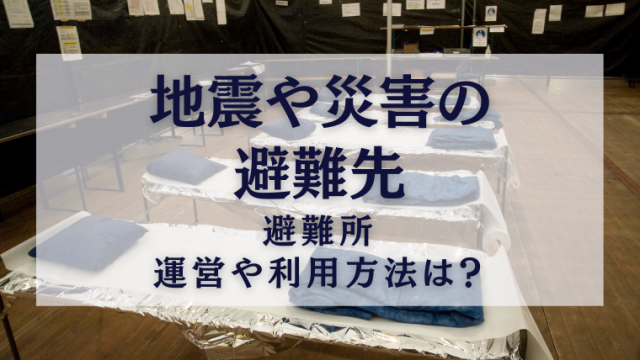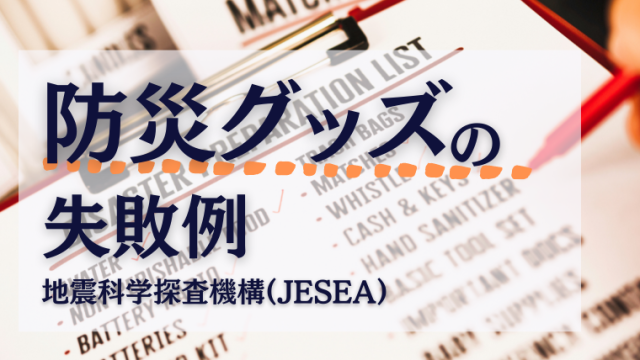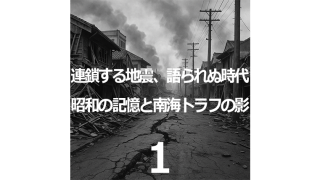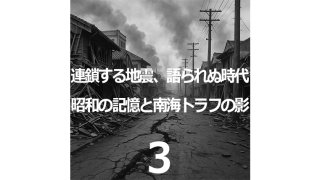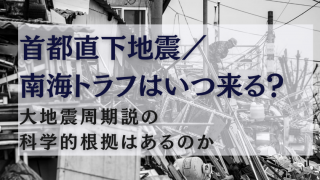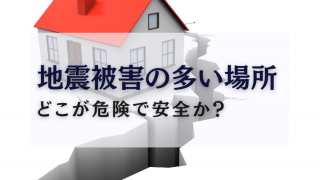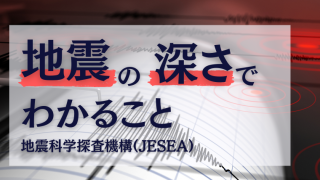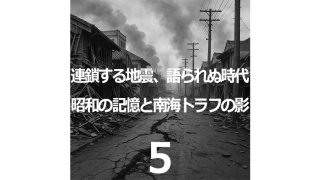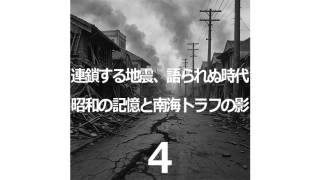【第2部】続発の記憶──三河地震から見る“第二波”の衝撃
1945年1月13日、真冬の未明。冷え込みの厳しい時間帯に、愛知県西部を中心に強い揺れが襲った。前年12月の昭和東南海地震から、わずか1か月余り。この地震は「三河地震」と呼ばれ、死者2300人を超える大惨事となった。
しかしこの地震の存在は、意外なほど知られていない。戦時下という特殊な事情が重なり、地震の詳細な記録も報道もほとんど残されなかったからである。当時の新聞は「若干の家屋倒壊」といった表現で済ませ、その深刻さを伝えることはなかった。
最も大きな被害を受けたのは、岡崎市、安城市、碧南市、西尾市など西三河地方の広範な地域だった。特に安城市では、軍需工場である中島飛行機安城製作所が倒壊し、多くの若者や勤労動員中の学生が犠牲となった。工場周辺の住宅地も壊滅的な打撃を受け、あたり一帯はまるで戦場のようだったという。
夜中の3時過ぎ、寝静まっていた住民たちは、突如として襲った縦揺れに飛び起きた。木造家屋は音を立てて崩れ、土壁がはがれ、瓦が飛び散った。布団にくるまれたまま逃げられなかった人、柱の下敷きになった人。家族を助けようと戻った者が命を落とすことも少なくなかった。
火鉢や囲炉裏が倒れ、地震の直後には各所で火災が発生した。安城市のある町では、倒壊した住宅街が炎に包まれた。水道も断たれ、住民たちは雪を溶かして火を消そうとしたという。夜明けまでの数時間が、どれほど長く、絶望に満ちたものだったか。生き残った人々の証言には、今もあの夜の記憶が色濃く残る。
にもかかわらず、三河地震は歴史の表舞台に立つことなく、やがて忘れられていった。戦局の悪化がその最大の理由だった。1945年初頭、日本は本土空襲の脅威に直面しており、情報統制はより一層強化されていた。行政の対応も後手に回り、支援も救援も限定的なまま、被災地は孤立した。
被災者たちは、自力での復旧を強いられた。家を失った人々は、壊れた蔵や畑の小屋に身を寄せ、雪の舞う中で布団を敷き、寒さをしのいだ。安否確認の通信手段も乏しく、親戚の消息がわかったのは終戦後というケースもあったという。
また、学生や若年労働者を多く抱えていた工場の被害は、地元に深い傷を残した。若者たちが亡くなったことを悔やむ家族は、声を上げることも許されなかった。国家のために働いていた彼らの死は、いつしか「名誉の死」として処理され、その真相は闇に葬られた。
それでも、地元にはひっそりと残された記録がある。ある旧家には、当時の出来事を克明に綴った日記が残されていた。そこにはこう記されていた。「戦争のせいで誰も何も言わない。けれど、この地震の方が、家族を、町を、壊した」
現在、三河地震の被災地には、いくつかの慰霊碑が建てられている。その多くが目立たぬ場所にあり、訪れる人も少ない。だが、石に刻まれた名前は、確かにそこに生き、突然命を絶たれた人々の存在を今に伝えている。
この地震は、東南海地震と南海地震の“間”に発生した災害である。しかも直下型。つまり、地震には連鎖性があることを私たちに教えてくれる重要な出来事だった。
三河地震は、戦争の陰に隠れ、口にすることさえはばかられた災害だった。だが、だからこそ、今私たちが語らなければならない。語られぬ死を忘れず、語る責任を引き受けてこそ、次に備える意味があるのではないか。
戦後、ようやく少しずつ地元の町史や個人史の中で三河地震が言及されるようになった。だが、それはほんの一握りの記録にすぎない。記憶が風化する前に、語り継ぐ者が必要だ。
私たちの足元は、決して安定しているわけではない。過去を忘れることは、未来の危機に背を向けることと同じだ。三河地震という“語られなかった災害”を今、改めて見つめ直す時が来ている。
(第2部・了)