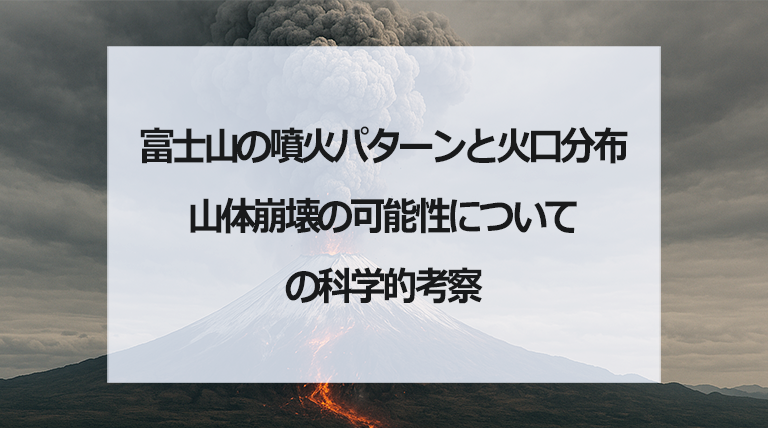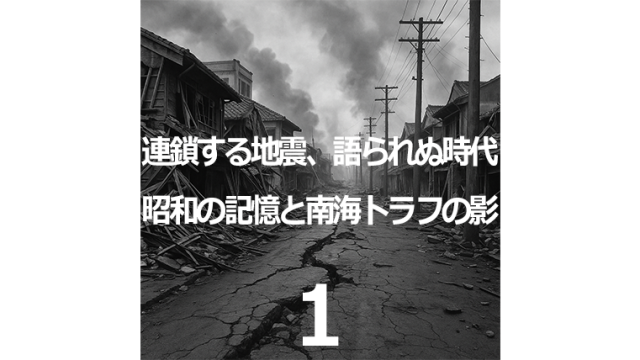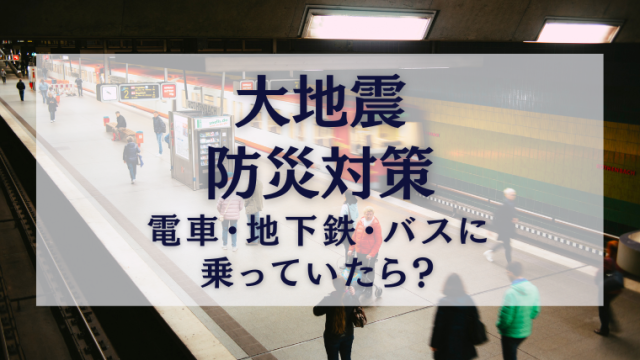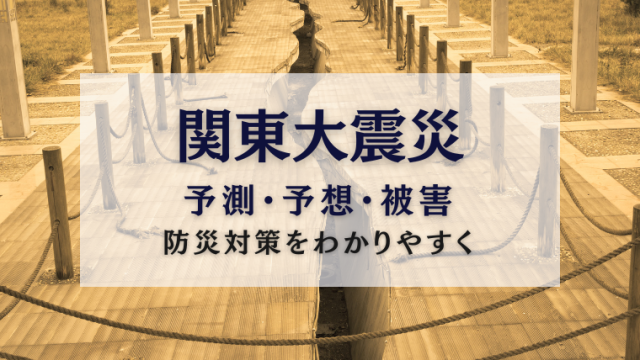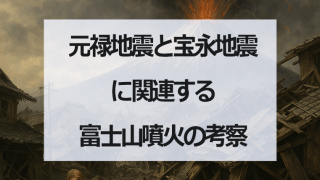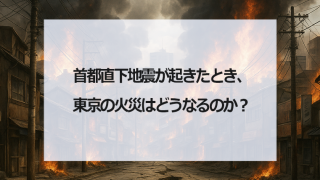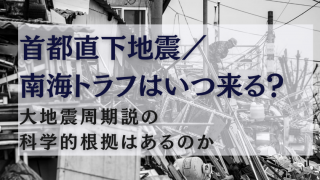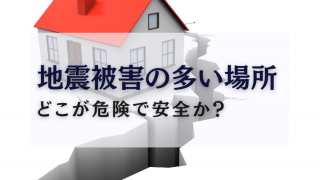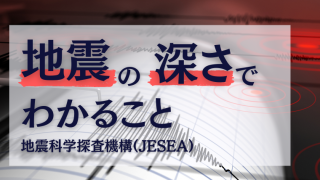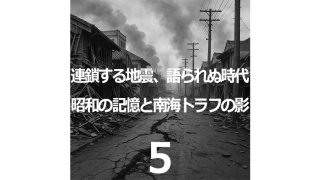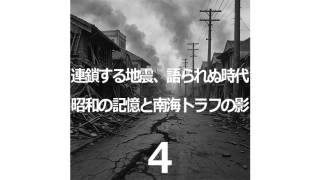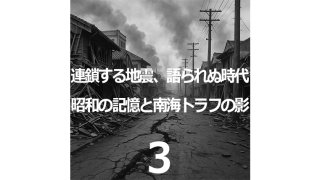1. はじめに
富士山は日本最大の成層火山であり、過去数万年間にわたって噴火を繰り返してきた活火山である。過去の噴火記録や地質調査に基づくと、富士山の噴火には一定のパターンがあり、火口の分布や噴火の特徴には時代ごとの変化が見られる。また、成層火山である富士山では大規模な山体崩壊が発生する可能性も指摘されており、噴火とともに重要なリスクとして考慮する必要がある。本稿では、過去の噴火事例をもとに、富士山の火口分布、噴火パターン、および山体崩壊の可能性について考察する。
2. 富士山の噴火の分類と火口分布
富士山の噴火は、大きく「山頂噴火」と「側噴火(側火口噴火)」に分類される。過去の噴火データに基づくと、火口の分布には以下のような特徴がある。
2.1 山頂噴火(約2300年前まで)
山頂噴火とは、富士山の頂上部に火口が形成される噴火を指す。約2300年前までは山頂からの噴火が継続的に発生していたが、それ以降は確認されていない。山頂噴火が発生しなくなった要因としては、地下のマグマ供給経路の変化や山頂部の固結が考えられる。
2.2 側噴火(側火口噴火)
富士山の2300年前以降の噴火は、すべて山腹や山麓の側火口から発生している。過去の主要な側噴火の事例として、以下のものが挙げられる。
• 約2900年前(御殿場泥流噴火)(山麓東側)
o 泥流を伴う噴火が発生し、広範囲に影響を与えた。
• 約2200年前(須走火口群噴火)(東斜面)
o 火砕流を伴う噴火が発生し、火山灰を広範囲に降らせた。
• 864年〜866年(貞観噴火)(北西斜面・長尾山火口群)
o 大量の溶岩流を伴い、現在の青木ヶ原樹海を形成。
• 1083年(剣丸尾溶岩噴火)(南東斜面・剣丸尾火口群)
o 溶岩流が流出し、現在の御殿場市周辺に影響を与えた。
• 1511年(大沢噴火)(南西斜面・大沢火口)
o 比較的小規模な爆発的噴火。
• 1707年(宝永噴火)(東南斜面・宝永火口)
o 富士山最大級の爆発的噴火で、大量の火山灰が関東地方に降り積もった。
3. 山体崩壊の可能性
富士山は成層火山であり、山体崩壊のリスクを持つ火山のひとつとされている。成層火山は、噴出物が積み重なって形成されるため、構造的に脆弱な部分が存在し、大規模な崩壊が発生することがある。
3.1 過去の山体崩壊の事例
富士山では過去に大規模な山体崩壊が発生した形跡がある。代表的な事例として、**御殿場泥流(約2900年前)**が挙げられる。このとき、山体の一部が崩壊し、大規模な土石流(ラハール)が発生したと考えられている。
3.2 山体崩壊の発生メカニズム
富士山の山体崩壊は、以下の要因によって引き起こされる可能性がある。
• 噴火による山体の不安定化
o 側噴火が発生すると、山体の一部が弱くなり、崩壊の引き金となる可能性がある。
• 地震の影響
o 富士山周辺はプレート境界に位置しており、大規模な地震が発生する可能性がある。これにより山体が崩壊するリスクが高まる。
• 長期間の風化や侵食
o 長年の降雨や侵食によって、山体が徐々に弱くなり、大規模な崩壊が発生する可能性がある。
3.3 山体崩壊が引き起こす被害
• 大規模な土石流(ラハール)
o 富士山周辺の河川を通じて泥流が流れ下り、広範囲に被害をもたらす可能性がある。
• 溶岩ドームの形成と二次的な噴火
o 崩壊後に新たなマグマが上昇し、爆発的な噴火を引き起こす可能性がある。
• 首都圏への影響
o 山体崩壊に伴う火山灰の大量放出により、東京を含む関東圏で大規模な降灰被害が発生する可能性がある。
4. まとめと今後の考察
• 富士山の噴火は2300年前以降、すべて側噴火として発生している。
• 山体崩壊のリスクが存在し、特に東南斜面(宝永火口周辺)や北西斜面(青木ヶ原方面)が危険性が高い。
• 将来的な火山活動の監視と防災対策が重要である。
5. 富士山の噴火に関する諸説
富士山の噴火パターンや山体崩壊に関する研究は現在も進行中であり、さまざまな仮説が提唱されている。一部の研究では、次の噴火はこれまで噴火がなかった地域から発生する可能性も示唆されている。また、マグマの供給システムに関する新たな解析によって、これまで考えられていたよりも噴火の周期が短い可能性も指摘されている。
噴火のメカニズムには依然として未解明な部分が多く、火山活動の監視を継続し、最新の研究をもとに防災計画を適宜更新することが不可欠である。