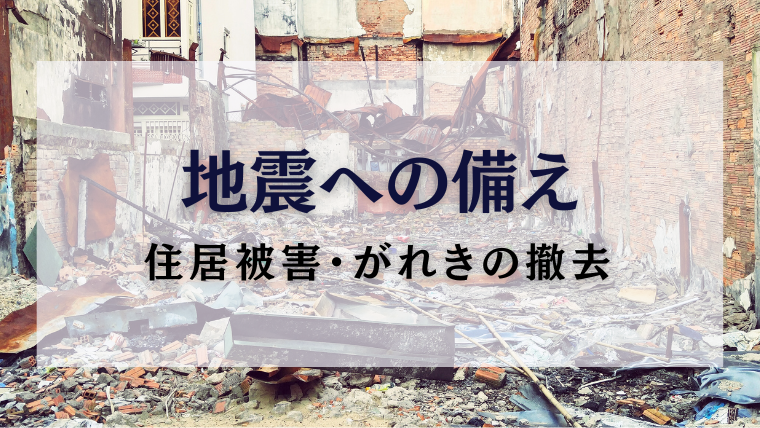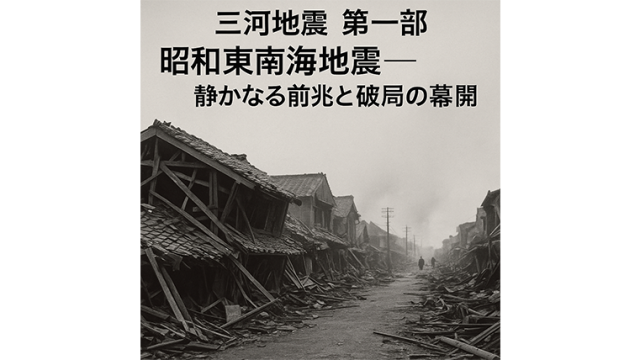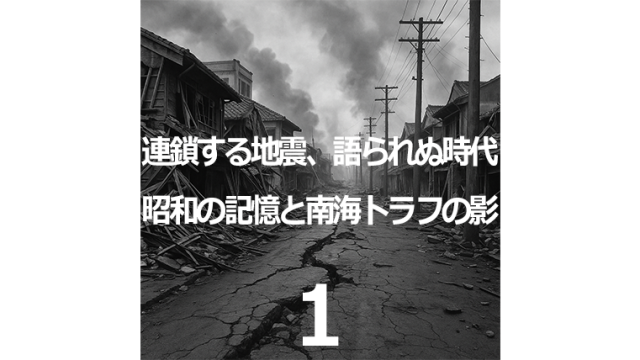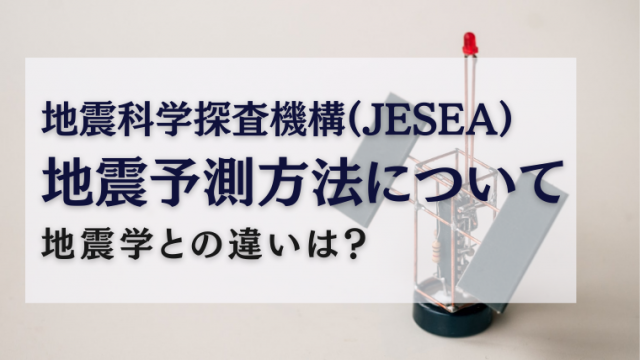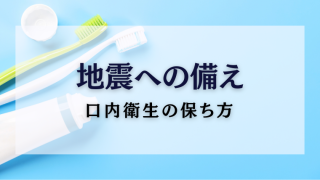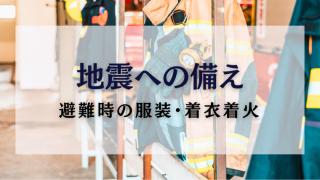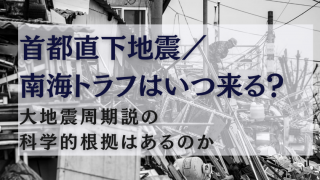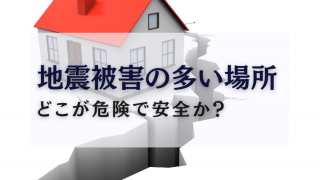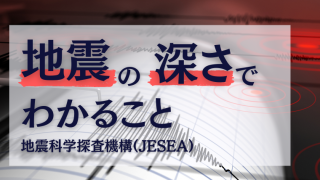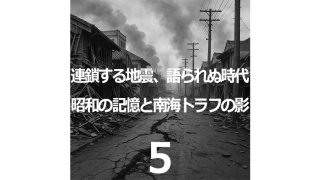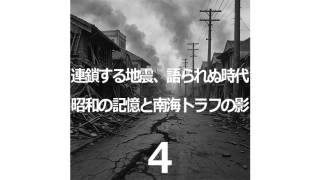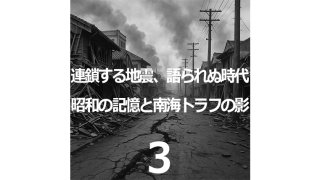JESEA Blogではこれから先、
いつ起こってもおかしくはないといわれる大地震に対し
今から備えるために、避難や防災に役立つ知識をご紹介しています。
今回は、地震によって住居に被害を受けた場合に
どのような手順で復旧していけばいいのか、
罹災証明書と被災証明書の違いなどを説明していきます。
罹災証明書と被災証明書
地震に限らず、災害により被害を受けた場合、
被害を受けたという証明を取得することで、
各種支援金や税金の減免を受けられる場合があります。
被害を受けたことを証明するために使われるのが
「罹災証明書」と「被災証明書」です。
「罹災証明書」は「家屋の被害」を証明するもので、
「被災証明書」は「住宅以外」に対する被害を証明します。
「被災証明書」が対象にするのは、
自動車、家財、屋外の設置物、店舗や工場です。
「罹災証明書」は被害の原因や程度を証明するもので、
各自治体が発行する公的な書類です、
被害の程度に基づいて、利用できる支援の内容が異なってきます。
主に支援や税の減免申請に必要となるため、
住宅に被害を受けた場合は取得することをおすすめします。
これらの証明書は各自治体により、被害状況の調査が行われたり
被害を受けた家屋の写真等を確認してから発行されるという手続き上、
申請してから手元に届くまでに時間がかかることがあります。
証明書が必要になることを見越して、早めに申請しておくと安心です。
罹災証明書の取得の流れ
災害により住宅が被害を受けた場合は、
まず被害箇所と被害の内容がはっきりわかるような写真を撮影します。
スマートフォンのカメラでも構わないので、
なるべくはっきりと被害の様子が把握できる写真を撮影しましょう。
まず住居を四方向から、全体が映るように撮影し、
その後住宅内の各被害箇所を撮影するようにします。
浸水があった場合には、浸水で水が上がってきた痕跡も
撮影するとよいでしょう。
屋外にある車、倉庫なども被害を受けていれば撮影をします。
被害箇所の様子がわかる写真と、
身分証明書等の必要書類を揃えてから
自治体に罹災証明書や被災証明書の申請を行います。
申請後、申請を受けた自治体が
各現場に調査員を派遣し、被害状況の確認を行います。
この確認が完了次第、証明書の発行が行われます。
調査員により1次調査が行われ、その後調査内容や判定に不服がある場合のみ、
2次調査が申請できるようになっています。
自治体によっては、現地調査を行わずに
写真の確認のみで罹災証明書の発行を行う自治体もあるため
実際の申請手順や内容については、お住いの自治体の内容を確認してください。
罹災証明書を使って受けられる公的支援は、現在9種類存在しています。
内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要(令和6年6月1日現在)」に
まとめられていますので、制度利用を検討する際に参考にしてみてください。
がれきの除去や解体
災害により住宅が被害を受け、修繕ではなく解体が決まった場合は、
罹災証明書の受け取り終了後に工事が行われることになります。
解体業者については、原則自治体の指定業者が行います。
地震により地域全体の住宅が被害を受けた場合には、
より被害程度が激しい、または倒壊の危険がある場所を優先して
解体工事やがれきの撤去作業が進んでいくため、
解体の順番や時期については住宅所有者の任意ではなく
状況次第であることに注意が必要です。
状況次第であっても、早めに罹災証明書の申請まで済ませることで
解体工事の順番にも早く加われることになるため、
住宅が大きな被害を受けた場合には、まず罹災証明書の取得を
優先して進めるようにすると、後の避難生活の懸念も軽減できます。
解体後に発生したがれきは、
以前このブログでも紹介した通り、「災害廃棄物」として処理場に運ばれます。
しかし処理場がいっぱいになったり置き場がなくなった場合は
一次的に敷地内に置いておく必要が生じるケースがあります。
また、住宅の被害について、特に公費による支援を利用したい場合は
罹災証明書や被災証明書が必要になりますが、
「間違いなく災害による被害か」を証明するために
証明書の申請期限が定められていることに注意が必要です。
申請期限についても自治体によって異なっているため、
詳しくはお住いの自治体の情報を確認するようにしてください。
今回は災害時に申請できる罹災証明書や、
住宅が被害を受けた場合の流れについて説明しました。
次回も災害時に役立つ情報をお届けしていきます。