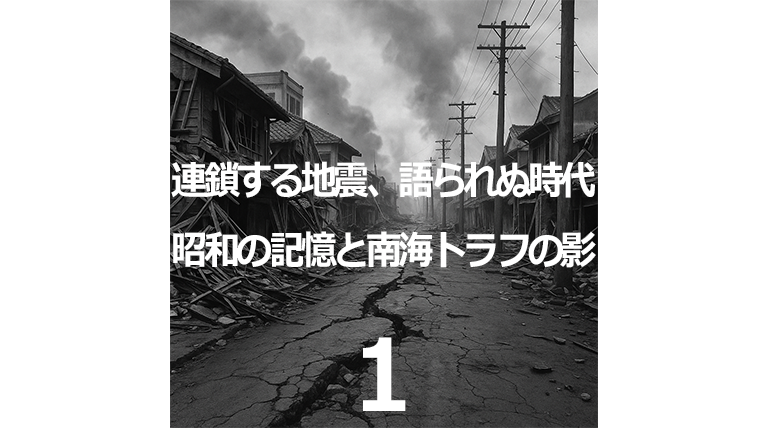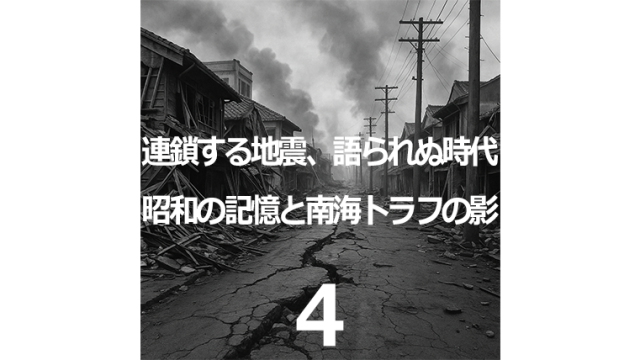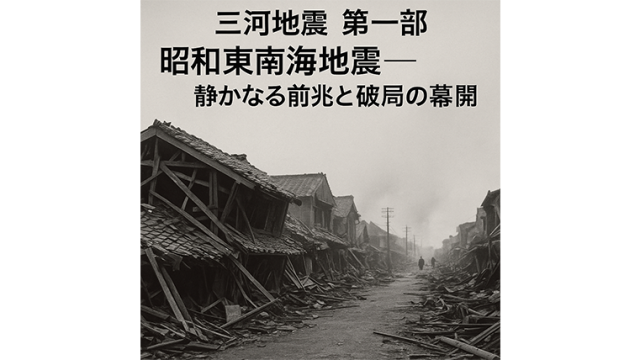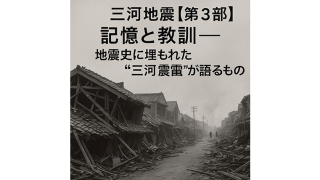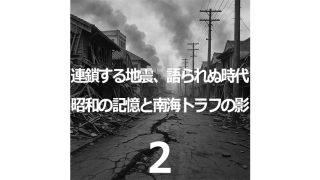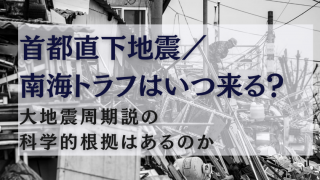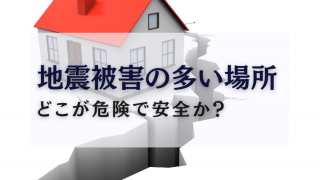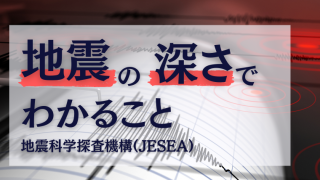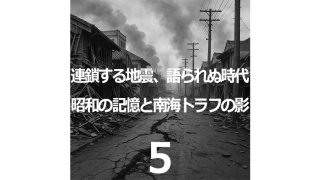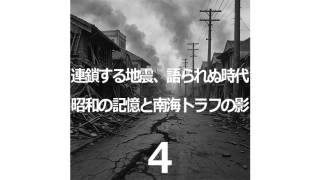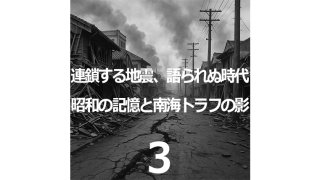【第1部】不穏な連鎖の始まり──昭和東南海地震とその前夜
1944年12月7日、午前1時36分。太平洋戦争末期の日本に、想像を超える地震が襲いかかった。この日発生したのが、昭和東南海地震である。三重県沖を震源とするこの地震は、紀伊半島から東海地方一帯に深刻な被害をもたらしたが、当時の新聞はこれを大きく報じなかった。
奇しくもこの日は、真珠湾攻撃から3年目にあたる日でもあった。軍国主義の色濃い時代、災害は「動揺を招く」として国民に知らされることは極力避けられた。事実、この巨大地震による津波や建物倒壊、死傷者の情報は、ほとんど国民の目に触れることなく、統制の名の下に封じられた。
三重県尾鷲市、志摩地方では津波の被害が大きく、漁港の船は壊滅的な打撃を受けた。愛知県では豊橋、蒲郡、知多半島などで家屋倒壊が相次ぎ、山間部では土砂崩れが発生した。だが、戦局は悪化し続け、空襲への警戒が強まるなか、人々の関心は空からの脅威に偏っていた。
愛知県内の工場地帯でも被害は出た。中島飛行機、豊川海軍工廠など、軍需生産を担う施設が揺れに見舞われ、作業中だった多くの労働者や学生動員が負傷した。それでも、これらの情報は機密とされ、翌日の新聞では「東海地方でやや強い地震、若干の被害」などと簡単に触れられるのみだった。
一方で、地震の揺れを体験した市民の証言には、通常の地震とは異なる不安がにじんでいた。「海鳴りがして、畳が浮いたようだった」「犬が狂ったように吠えていた」──そんな異変の記憶が、個人の日記や地域の記録にわずかに残されている。
当時、各地の小学校では生徒が避難訓練もないまま机の下に潜り込んだ。教員たちは「落ち着け、空襲ではない」と繰り返したが、地面から響く音と壁のきしみで、多くの児童が恐怖に凍りついた。工場では自動機械が停止し、煙があがり、警報ではなく地鳴りによって人々が外へ飛び出した。
夜が明けると、沿岸部の村では津波の被害が広がっていた。田畑は海水に浸かり、舟は屋根の上に乗り上げていた。人々は呆然と立ち尽くし、「戦争中だから仕方ない」と言い聞かせるように片付けを始めたという。だが本音では、「次にまた何かが来るのでは」との不安が、心の奥底に根を張っていた。
さらに深刻だったのは、通信網と鉄道への影響である。国鉄は一時的に運行停止となり、電報や電話も不通になった地域が多かった。被害情報が集まらず、行政の対応も後手に回った。だがそれらの遅れは戦況悪化の中で見過ごされ、「震災より空襲への備えが優先」とされてしまった。
被災地では、自治体の職員や消防団が限られた人員で復旧作業に当たった。防空壕に避難していた住民の多くが、地震の発生で一時的に屋外へ飛び出すなど混乱も見られたが、それすら報道されることはなかった。地震と空襲、二重の脅威にさらされながらも、人々は声を潜めて日常を維持しようとしていた。
食糧難が深刻化する中で、被災者に対する支援はほとんど届かなかった。倒壊した家から持ち出したわずかな食料と衣類で数日間をしのぎ、親戚を頼って避難する家族も多かった。だが疎開先でも歓迎されるとは限らず、厳しい視線にさらされることもあったという。
このような状況にあっても、地域の人々は助け合いながら日々を生き延びた。井戸水を分け合い、土間に布団を敷いて見知らぬ家族を泊めるなど、小さな善意が絶望の中で灯となった。だがそれらの行動もまた、記録に残ることは少なかった。
軍部や行政が「パニックを防ぐ」という大義名分で情報を抑えるなか、現場の人々は「これは序章かもしれない」という漠然とした不安を感じていた。そしてその予感は、わずか1か月後、現実のものとなる。
あの夜から始まった“連鎖”は、国家の命運と庶民の暮らしを根底から揺さぶる、時代のうねりの始まりだった。誰もが予測できぬ未来に不安を抱きながらも、その夜を越えるしかなかった。
(第1部・了)