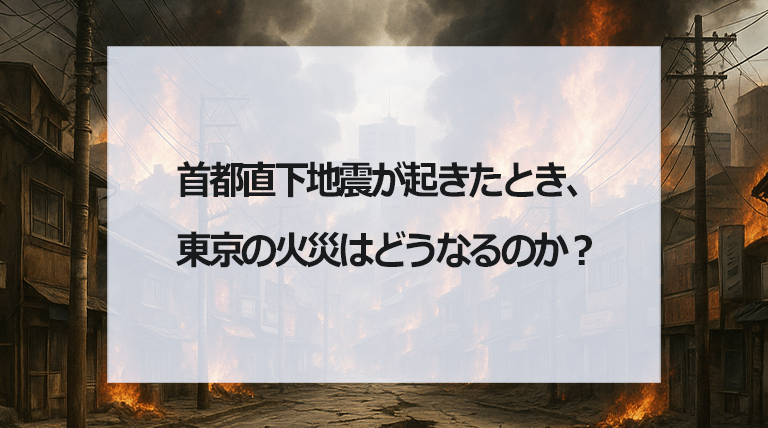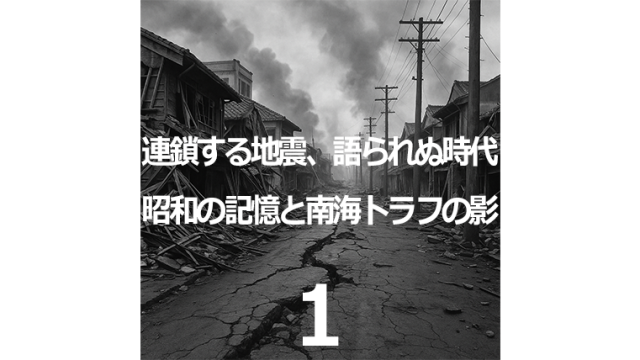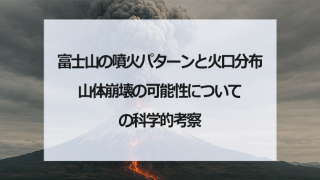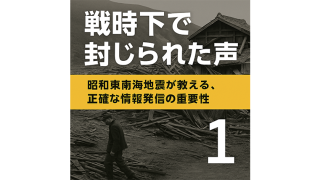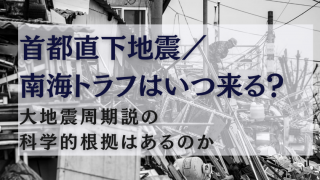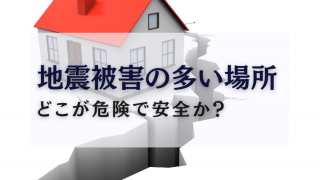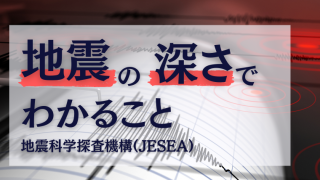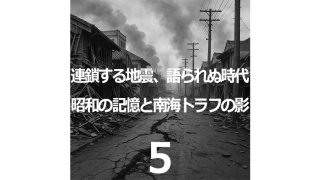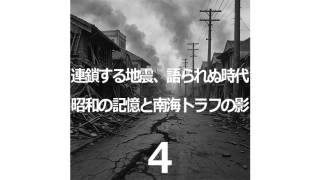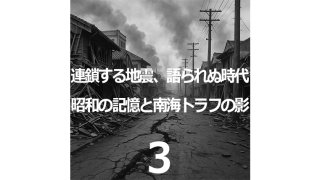もしも東京を直撃する首都直下地震が発生したら、私たちの暮らしはどうなるのでしょうか。地震そのものの揺れによる被害も深刻ですが、実は「火災」が大きな脅威になることをご存じでしょうか。
内閣府や東京都が発表している被害想定では、冬の夕方にマグニチュード7クラスの地震が直下型で発生した場合、東京23区内では約2,000件以上の火災が同時多発的に発生する可能性があるとされています。
火災の原因はさまざまです。たとえば、ガス漏れや電気配線の損傷、調理中の火の消し忘れなど。特に夕食の準備中に地震が発生すれば、火の元が各家庭で一斉にトラブルを起こす危険があります。加えて、建物の倒壊によって逃げ遅れたり、初期消火ができなくなったりするケースも少なくありません。
では、そんなときに頼りになる消防車は、果たして間に合うのでしょうか?
東京消防庁は、約1,800台の消防車両を保有し、日頃から都内の消防活動にあたっています。しかし、同時に2,000件以上の火災が発生した場合、それらすべてに対応するのは物理的に不可能です。しかも、大地震の直後は道路が寸断されたり、倒壊した建物のがれきで道がふさがれたりするため、消防車が現場に到着するのにも大きな時間がかかると想定されています。
さらに問題なのが、119番通報の状況です。震災時には通報が殺到し、電話回線がパンクすることも考えられます。普段ならすぐに繋がるはずの119番が、何度かけても繋がらない。ようやく通報できたとしても、消防が来られるかどうかはまた別の話です。
仮に消防車が来られたとしても、限られた台数で、燃え広がる火災に対して十分な水や人員を確保するのは難しいとされています。つまり、火災の延焼は広がる可能性が高いというのが現実なのです。
東京都の資料によれば、こうした状況下では木造住宅が密集する地域を中心に、火災による延焼が最大で700ヘクタールに達するとも言われています。これは東京ドーム150個分以上の広さに相当します。しかも風が強ければ、「火災旋風(かさいせんぷう)」と呼ばれる竜巻のような火災が起き、火の粉が遠方まで飛び火するリスクもあります。
1923年の関東大震災でも、火災による被害が特に甚大で、多くの命が奪われました。その教訓を私たちは忘れてはいけません。
ではどうすればよいのでしょうか。
行政機関や消防署では「自助・共助・公助」の考え方を基本にしています。「公助」、つまり消防や行政の力には限界があります。だからこそ、私たち一人ひとりが「自助」――家具の固定、火の元の管理、消火器の設置、避難ルートの確認などを行うことが重要です。そして、地域の住民同士が協力しあう「共助」――マンションや町内会単位での防災訓練や、消火器の使い方を確認し合うことも大切です。
特に初期消火ができるかどうかで、火災の被害規模は大きく変わります。消防庁の統計によると、火災発生から最初の3分間がカギだとされています。消火器やバケツリレーで火を小さくとどめられれば、大規模な延焼を防ぐことができます。
つまり、消防車に頼りきるのではなく、自分たちの備えが何よりも重要なのです。
大地震が起きたそのとき、119番にかけても消防車はすぐには来られないかもしれません。そんなとき、命を守るのは日頃の準備と地域の連携です。防災は、特別な人だけの仕事ではありません。誰かに頼るのではなく、「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識を、今こそ育てていくことが求められているのではないでしょうか。