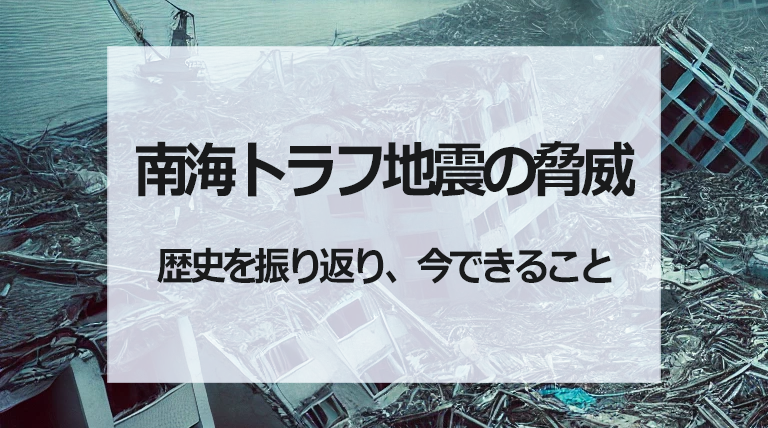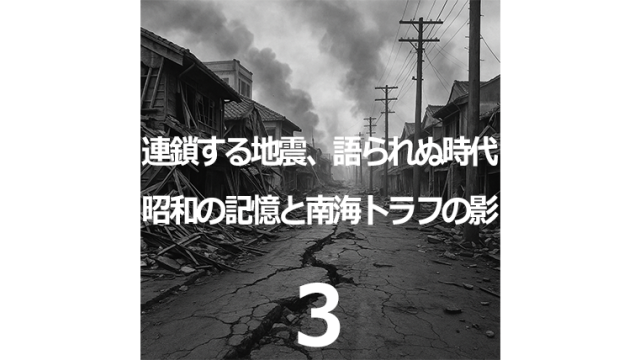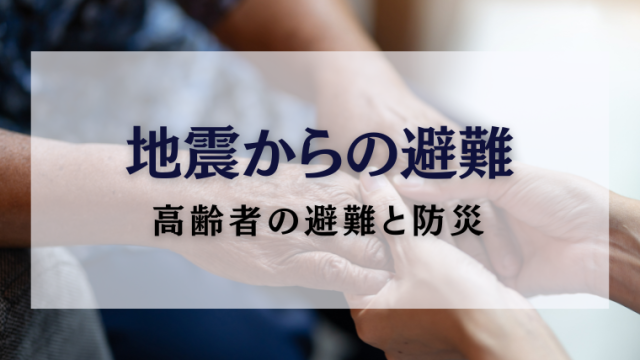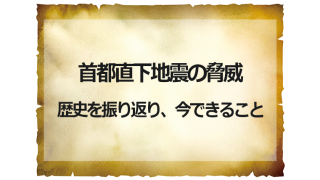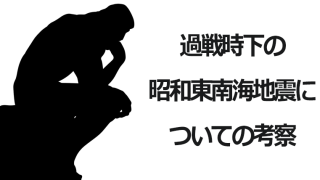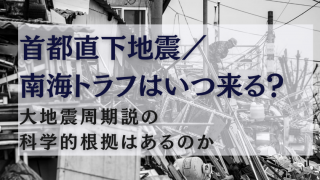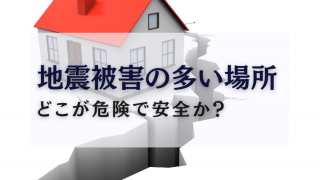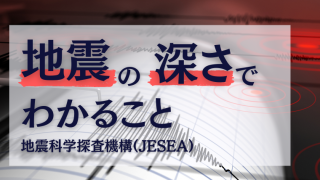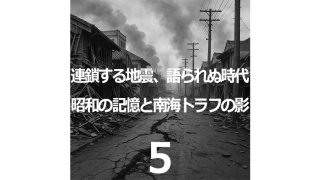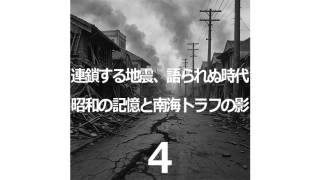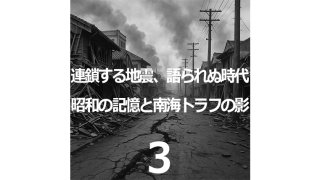過去の事例から見る南海トラフ地震
南海トラフ地震は、日本の太平洋沿岸地域に甚大な被害をもたらしてきた巨大地震の一つである。歴史を振り返ると、宝永地震(1707年)、安政東海地震・安政南海地震(1854年)、昭和東南海地震(1944年)、昭和南海地震(1946年)と、約100年から150年周期で発生している。
宝永地震(1707年)
宝永地震は、マグニチュード8.6と推定される巨大地震であり、東海・東南海・南海地震が連動して発生した例である。この地震は広範囲にわたる震動と津波を引き起こし、さらにその49日後には富士山の宝永大噴火を誘発した。宝永大噴火は、江戸時代の日本社会に大きな影響を与えた。
安政東海地震・安政南海地震(1854年)
安政年間には、東海と南海で1日違いで地震が発生した。安政東海地震(M8.4)は12月23日に発生し、翌日の12月24日には安政南海地震(M8.4)が続いた。このような連動型の地震は、南海トラフ地震の特徴の一つである。
昭和東南海地震・昭和南海地震(1944年・1946年)
昭和東南海地震は1944年に発生し、M8.0の規模で東海・東南海地方に甚大な被害をもたらした。その2年後の1946年には昭和南海地震(M8.4)が発生し、四国から紀伊半島を中心に大きな被害を受けた。この2つの地震により、南海トラフにおけるプレートの歪みが解消されたと考えられている。
未来の南海トラフ地震と首都直下地震・富士山噴火の連動の可能性
近年の地震研究では、南海トラフ地震が首都直下地震や富士山の噴火と連動する可能性が指摘されている。過去の宝永地震では、南海トラフ地震の約2か月後に富士山が大規模噴火を起こしている。このことから、今後の南海トラフ地震でも同様の現象が起こる可能性がある。
また、南海トラフ地震の発生時には、プレート全体が影響を受けるため、首都圏でも大規模な地震が発生する恐れがある。特に、フィリピン海プレートと太平洋プレートの境界にある関東地方では、地震の連鎖反応が起こる可能性があり、首都直下地震との関連が懸念されている。
さらに、南海トラフ地震が発生した際には、地下のマグマ活動が刺激され、富士山噴火が誘発される可能性がある。現在、富士山は300年以上噴火していないが、マグマ溜まりの状態は活発化していると考えられており、南海トラフ地震との関連が無視できない状況にある。
今後の対策と「MEGA地震予測」の有効性
このような大規模地震に備えるためには、ハードとソフトの両面での対策が不可欠である。耐震建築の普及や津波対策の強化に加え、個人レベルでの防災意識の向上も求められる。
また、近年注目されている地震予測技術の一つに、「MEGA地震予測」がある。この予測システムは、特許技術を活用し、様々な前兆現象を捉え高精度に分析することで、地震発生の可能性を事前に察知することを目指している。完全な予知は難しいものの、リスクの高い地域を特定し、防災対策を強化することに貢献できる可能性がある。
南海トラフ地震が発生した場合、過去の事例から見ても甚大な被害が予想される。そのため、過去の地震から学びつつ、最新の予測技術を活用し、可能な限りの備えを行うことが重要である。