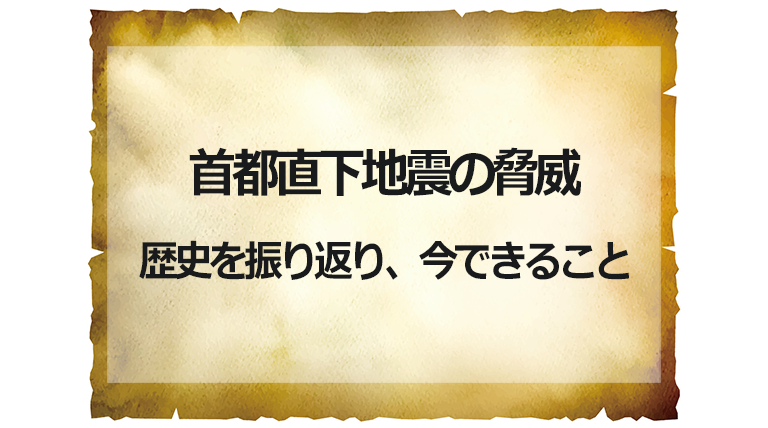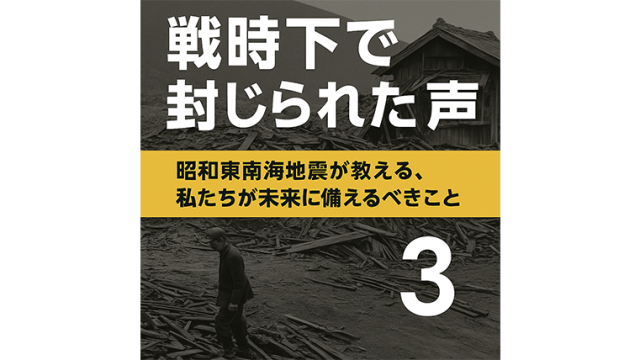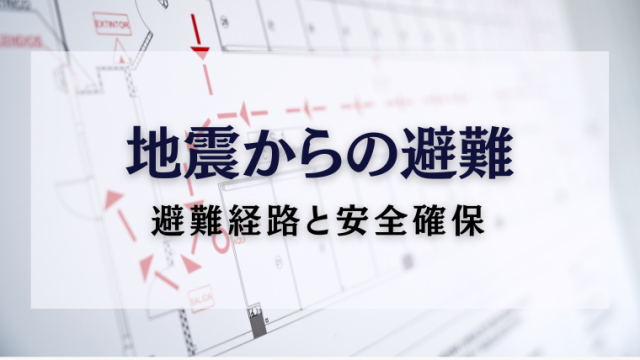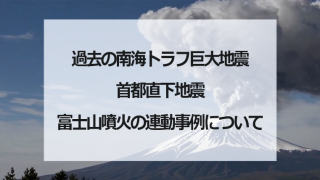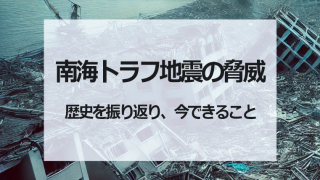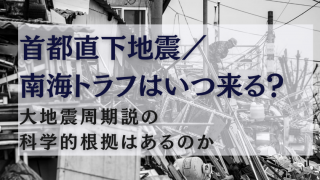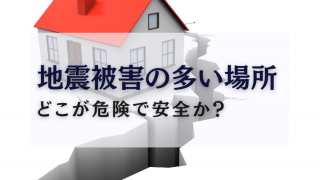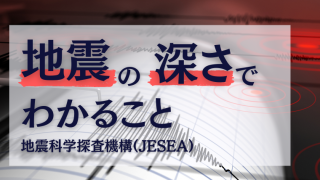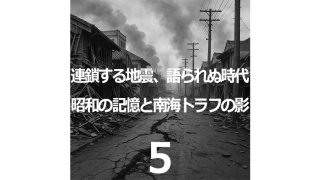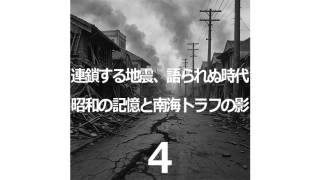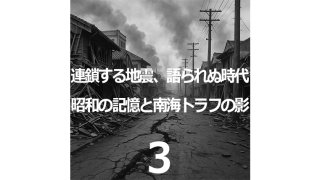過去の首都直下地震の事例
首都直下地震とは、日本の首都圏で発生する大規模な地震を指します。歴史的に見ても、東京を中心とした地域では、繰り返し大きな地震が発生してきました。ここでは、代表的な3つの事例を紹介します。
① 元禄地震(1703年)
元禄16年(1703年)に発生した元禄地震は、相模トラフ沿いで発生した大地震で、推定マグニチュード8.2とされています。地震の影響で江戸(現在の東京)でも強い揺れが発生し、多くの建物が倒壊しました。さらに、この地震に伴う津波が房総半島から伊豆半島にかけて甚大な被害をもたらし、多数の死者が出ました。
② 安政江戸地震(1855年)
安政2年(1855年)に発生した安政江戸地震は、マグニチュード7.0程度と推定される地震で、江戸市中に甚大な被害をもたらしました。この地震は、直下型地震であり、揺れが激しく、火災が同時多発的に発生しました。地震と火災により、江戸の街では約1万人が犠牲になったとされています。
③ 関東大震災(1923年)
大正12年(1923年)9月1日に発生した関東大震災は、首都圏の歴史の中でも最も被害が甚大な地震の一つです。マグニチュード7.9とされるこの地震は、相模トラフを震源として発生し、東京・神奈川を中心に甚大な被害をもたらしました。特に、地震発生直後に広範囲で火災が発生し、死者・行方不明者は約10万5千人に上るとされています。関東大震災を契機に、日本の防災意識は大きく変化しました。
これから予想される首都直下地震
政府の地震調査委員会によると、今後30年以内に首都直下地震が発生する確率は70%程度とされています。首都直下地震の発生メカニズムとしては、
フィリピン海プレートの沈み込みによる地震
内陸直下型の活断層による地震
南海トラフ巨大地震に関連する影響
などが考えられています。
特に、東京湾北部を震源とするマグニチュード7クラスの地震が発生した場合、23区内では震度6強の揺れが予想され、建物倒壊や大規模火災、交通網の寸断が懸念されています。また、ライフラインの寸断により、水道や電気、ガスなどの供給が停止するリスクも高くなります。
防災対策と地震予測の活用
首都直下地震への対策として、以下のような具体的な防災対策が求められます。
耐震補強の推進:古い建物の耐震補強を行い、倒壊リスクを低減する。
家庭での備え:非常食や飲料水の備蓄、家具の固定、火災対策の強化を行う。
地域での防災訓練:自治体や企業が主催する防災訓練に参加し、災害時の対応を学ぶ。
情報収集の徹底:防災アプリや最新の地震予測情報を活用し、防災意識を高めることも有効です。
特に、近年では「MEGA地震予測」といった最先端の地震予測技術が注目されています。これは、地殻変動データやその他の特許技術を基に地震発生のリスクを解析するものであり、リスクの高い地域を事前に把握することができます。このような情報を日頃からチェックし、首都直下地震への備えを強化することが重要です。
まとめ
首都直下地震は過去にも繰り返し発生しており、今後も発生する可能性が高いとされています。関東大震災のような大規模な地震が再び発生すれば、都市機能に壊滅的な影響を与える可能性があるため、個人・企業・自治体が協力して備えることが求められます。最新の地震予測技術を活用しながら、日々の防災対策を徹底することが、首都直下地震の被害を最小限に抑える鍵となるでしょう。